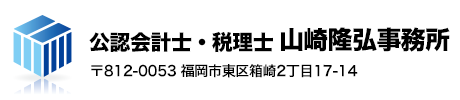保険・年金
保険・年金中小機構の経営セーフティ共済は、一般的には「倒産防止共済」と言われています。
そもそも経営セーフティ共済の趣旨は、取引先の倒産という事態に備えるために、不足の事態に直面した際に、必要資金を速やかに借入できる共済制度です。
共済金の借入が受けられるのは、法的整理、取引停止処分、災害による不渡り等、公に得意先が倒産した場合です。いわゆる夜逃げ等の場合には適用できません。
共済金からの借入は無担保・無保証人で貸倒債権の範囲内で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで可能です。制度の趣旨から売掛金の回収が困難になったときは速やかに借り入れることができます。無利子ということになっていますが、借入金の10%が共済の積立から控除されます。
このように得意先の倒産に備えての共済ですが、掛金が損金算入できるということで、納税を一旦回避するために使用されていることが多いようです。税制上の優遇措置が受けられるとHPにも案内されています。
月額掛金は5,000円~20万円まで自由に選べて、増額・減額ができます。前納もできます。1年以内の前納掛金は払い込んだ期の損金として計上できます。ただ、前納すれば1月につき1,000分の0.9だけ減額されます。個人事業主の場合は、不動産所得等の事業所得以外の収入には損金算入が認められていません。
解約はいつでもできますが、納付月数が12ヶ月未満の場合、解約手当金は受け取れません。なので、1年以内に解約することはあまり考えられません。40ヶ月以上掛けていれば100%戻ってきますが、1年超2年以内の解約であれば80%の解約金となります。40ヶ月までは掛け月数に応じて逓増していきます。
5年後に共済金が戻ってきたときには、雑収入で受け入れます。利益に計上しますので、ここで課税されます。期間を通してみれば、節税ではなくて、単なる課税の繰延です。その間、資金を自由に使えず、共済金が全額戻ってこない場合が種々想定されます。取引先の倒産防止という本来的な意味合いでの使用をお勧めします。
※動画でも解説しています。