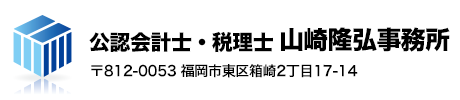キャッシュを残す経営
キャッシュを残す経営令和6年7月3日、20年振りに新札が発行されました。1万円札は渋沢栄一、5千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎です。渋沢栄一は2021年の大河ドラマで、吉沢亮が演じた『青天を衝け』では百姓でありながら、最後の将軍徳川慶喜に見出され、維新後の日本経済を作っていく様が描かれていました。城山三郎の『雄気堂々』の上下巻は、読みごたえがあります。2019年には今は世界遺産となっている、渋沢栄一が開いた富岡製糸場に行ってきました。
渋沢栄一がいなければ、日本の経済発展はなかったのではないかと思えるくらいに設立した会社の多さに驚きます。第一国立銀行(現在のみずほ銀行)三井住友銀行、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険の設立に係わっています。他に設立に係わった会社は電通、東京電力、東京ガス、王子製紙、サッポロビール、アサヒビールなどなどです。同じ時代の三菱創業者の岩崎弥太郎と違うところは、グループ企業を作っていないところです。渋沢の名前が残っているのは渋沢倉庫くらいです。ある程度、会社が軌道に乗ると、アッサリと譲っていっています。
経済アナリストの藤原直哉さんによると、新札を20年ごとに発行するのは、印刷局のお金をデザインして、彫刻する人の技を絶やさないためだそうです。タンス預金を表に出すために、新札を出すという説もありますが、日本銀行法では、過去に日本銀行から発行された銀行券は、一円未満の銀行券を除いて、通貨として使用できることとなっています。
なので、タンス預金があるからといって新札に交換する必要はありません。タンス預金といっても実際には自宅の金庫になると思います。お客様の金庫屋さんに教えてもらいましたが、火事になった場合は、1時間耐火、2時間耐火の金庫では、それ以上燃えると中の現金も燃えてなくなってしまいます。また、20年経過すると金庫を保護しているコンクリートの水分が蒸発してしまうので、20年ごとに買い換えることになります。
ですので、銀行の貸金庫に現金に保管することをお勧めしています。預金口座においておくと、NISAなど証券投資を勧められて面倒くさいことになります。現金で持っていると、今のようなインフレ時期には減るばっかりといいますが、ヘタに増やそうとして投資信託になどに投資すると半分になったりします。それに比べると、年間の保管料に1万円ほどかかっても安いものだと思います。