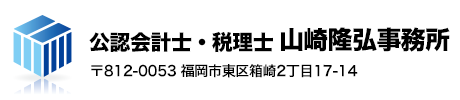キャッシュを残す経営
キャッシュを残す経営会計監査では、証拠力が強いものは、実査、立会、確認です。実査とは、実際に現金などを数えることであり、最も強い証拠力となります。立会とは、在庫の棚卸をしているところに立会うことであり、確認とは、銀行、証券会社に残高、取引を監査人が直接、確認することです。期末監査では、これらの監査手続を実施します。
期中監査での支店や、子会社などの往査では、まずは現金の実査をします。税務調査では突然ということはたまにはありますが、監査では事前に日程調整をして伺いますので、現金実査をして帳簿残高と一致しないことはまずありません。
税務調査では、申告後の決算書の調査であるため、現金実査を受けたことはありませんでしたが、最近の調査で初めて、現金実査を受けました。税務署でも世代交代が進み、定年近くの調査官と、20代の若い調査官のペアが多くなりました。新人研修の意味合いもあって、若い調査官に現金を数えさせていました。そこの会社では毎日、現金実査をして社長・会長に報告していますので、当たり前のように合いました。
経理の専任担当者がいない中小企業の場合、合わないことはままあります。たまに記帳資料に万札が混じっている会社もあります。近頃はキャッシュレス化が進み、個人でもあまり現金を使うことはなくなってきました。しかし、資産管理では現金を数えることは基本の中の基本です。
銀行口座にたくさんの残高があると、投資信託はNISAの営業を受けます。それを受けないように、会社によっては貸金庫を銀行から借りて、そこに現金を保管することを勧めています。バラの現金だと数えるのが大変ですが、100万円ごとの帯封だと数えやすいです。
銀行が発行する借入金の返済予定表はよくみますが、それと同様に、貯金の推移表はエクセルで作ってみます。毎月、これだけ貯めていけば、10年後、20年後、自分が死亡する時の残高がシミュレーションできます。生きていればの話ですが、時間が強力な因子になることが判ります。死亡時に残す資産の目安ともなります。