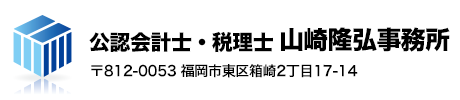キャッシュを残す経営
キャッシュを残す経営決算日が来る前に、決算対策としてお打合せをします。ここ最近は、特別な対策はほとんど不要の場合が増えてきました。利益が計画よりも多く計上され、従業員の方に還元する意味での賞与の計上は有用です。社員のモチベーションにも係わってきます。その場合は、決算日までに支払っていなければなりません。そうでなければ、決算日までに伝えたことを証明するものが必要となってきます。
他には、保険料を支払うことがありますが、倒産防止共済は800万円まで掛け金を積み立てることができ、全額損金となりますので、利用している会社は多くあります。取引先が倒産したときには、共済金の借入が無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで可能です。この本来の目的で掛ける分にはいいと思いますが、単に税金の支払を先に延ばすだけのためにするのは、お勧めしていません。
中小企業は、通常の実効税率34%のところ800万円までの利益(課税所得)までは、実効税率24%と約10%低くなります。ですので、課税の繰延をするのではなく、その都度、その年度で支払っていく方が資金的にも安定します。反対に、800万円が一度に課税となる方が大変です。全期間を通してみれば、少なくとも節税にはなっていません。
気をつけなければならないのは、利益が出たからと、余分な買い物をすることです。企業努力により残ったせっかくの利益を、無駄なものを買うことによって減らすのは、とてももったいないと思います。本当に必要なものはその都度、検討して購入しているはずです。
たとえ800万円利益がでても24%の税金ですので、192万円の法人税・住民税を支払えば、608万円残ります。800万円消費すると手残りゼロです。例えば、これを10年繰り返せば、6,080万円の預金になります。決算時にたくさん買物するとその支払と税金支払い時期が重なり、資金不足にもなりかねません。
賞与以外の決算対策は必要ないのではと思う今日この頃です。