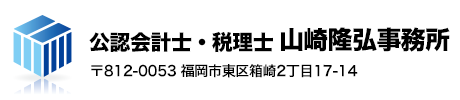元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
今回は、簿記の基本的なことを書いてみたいと思います。
「国際金融資本がひた隠しに隠す お金の秘密」
(成甲書房 安西正鷹著)を読むと、現在のマネーシステムがいかに仮想現実世界であるかについて、改めて驚くとともに、考えさせられます。
無から有を生み出す銀行の仕組みについても
詳しく明かしています。
ただし、「紙幣や硬貨という実体のあるモノとしてのお金にせよ、預金(信用貨幣)という記号としてのお金にせよ、複式簿記の知識なくしてお金の本質を十分に理解することはできない」と書かれています。
簿記とは「帳簿記入」の略語です。
簿記については、ゲーテが「複式簿記こそ人間の精神が発見した素晴らしいものの一つである」と
高く評価しています。
私は、いままでどうして左側(資産)が借方で、右側(負債)が貸方というのか、
疑問でなかなかなじめませんでした。
当たり前に考えると反対です。
そもそも簿記では共同事業でお金を出し合ってのパートナーシップ(個人)で記帳していました。
そのため、それぞれのパートナーが出資します。
出資した現金は左側に記帳されますが、相手勘定はパートナーにとっては貸付金となるため、
右側は貸方と呼ばれるようになりました。
パートナーシップが株式会社へ発展すると、株式会社の所有が個人となり、法人格として別になりますので、
複式簿記の性格が一変します。
出資者(株主)にとっての貸付金は、株式会社にとっての借入金になります。
株式会社の簿記では貸方に借入金が計上されることになります。
ちょっとややこしい話になってしまいましたが、私としては腑に落ちましたので、紹介させていただきました。