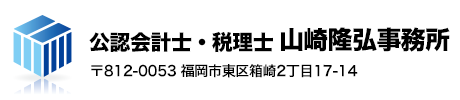経費
経費TBSドラマの『半沢直樹』が9月27日で終了しました。最終回の視聴率は44.1%と社会現象化するほどでした。後半は、銀行からの借入金を債務免除するかどうかのお話です。コロナ禍のため、新型コロナウイルス感染症特別貸付などにより、銀行からの借入金が増加傾向にあります。どの程度の借入金残高が適正であるのかとの問合せがあっています。
指標の一つに借入月商倍率があります。借入金を1ヶ月の売上で割ったものです。例えば、月平均売上が1千万円で借入金が2千万円あれば、借入月商倍率は2倍になります。一般的に借入月商倍率は2~3倍が適正とされます。しかし、これは運転資金に限ればともいえます。
設備投資であれば1億円を10年で借りた場合、1億円÷1千万円=10倍になります。だからといって即過大とはなりません。不動産投資などは10億円の借入ということもあり得ます。借入金10億円に対して、10億円の土地・建物が計上されることになります。問題は、この収益物件が返済可能金額を稼ぎだすかです。
法人の場合、返済の原資は、当期純利益+減価償却費です。減価償却費は既に支出しているものを、耐用年数にわたって費用化していくものですので、実際にはキャッシュは出ていきません。ですので、当期純利益に減価償却費を足したものが年間返済可能額となります。
借入金÷(当期純利益+減価償却費)が償還年数となります。年間返済可能額が1年間に返済する金額を上回っていなければなりません。そうでなければ、返済のために更に追加で借入をしなければならず、年々に膨れ上がっていきます。
また、短期借入金は一括返済できればいいですが、通常はなかなか難しいので、更新されていきます。金融機関の都合で更新されなかったり、更新の日数を開けられたりすると、いきなり倒産ということになりかねません。短期を長期に振り替えて、極力、返済していくようにしましょう。コロナ融資では返済開始を遅らせることもできるようになっていますが、その分、返済開始後の年間の返済金額が多くなりますので、気を付けましょう。