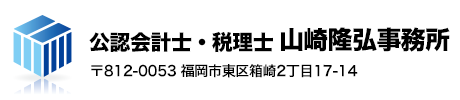その他
その他iDeCoは個人型確定拠出年金(DC)の愛称?です。60歳未満すべての人が利用できるようになっています。
私の場合は還暦を過ぎましたので、そもそもが対象外です。給付金は10年以上掛けていないと60歳からは受給可能とはなりません。加入期間が短いほど、受給可能年令が上がっていきます。
確定拠出年金は、銀行や証券会社などの管理会社が用意した金融商品を選択して運用する仕組みです。金融機関を通すので月間600円ほどの管理料を取られるようです。
要は「投資」ですので、当然リスクがあります。お客様が投資信託等で損失する場面に遭遇しますので、基本的に金融投資はお勧めはしていません。例えば投資信託で半分に目減りしても、それについて説明がなされることはほぼありません。
会社の場合は、その損失は費用計上できますが、個人の場合は何ら所得から控除されることはありません。ですので、iDeCoは税務上のメリットがあると喧伝されますが、それを上回る損失のリスクが十分あります。
一応、税務上のメリットと言われているものを確認すると、1つ目に、掛け金が全額所得控除されます。2つ目に運用益は非課税となっています。通常であれば投資信託の運用益等は、約20%の源泉所得税が控除されますが、非課税となります。運用益が発生すればということで目減りすれば、何の控除も受けられません。3つ目は、年金として受け取るときは公的年金控除が受けれます。また、退職所得として一時金で一括受給することもできます。
しかし、60歳になるまでは引き出すことができません。これが最大のデメリットだと思います。50代は子どもの教育資金でお金が出ていく世代ですが、年金資産に手をつけることはできません。
また、iDeCoの地雷と言われているものがあります。掛け金の積立金について年率1.173%を課税する特別法人税があります。制度上は企業型でも個人型(iDeCo)でも課されます。今のところ2023年3月31日までは、課税は凍結となっています。
※動画でも解説しています。