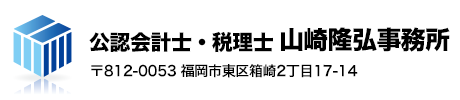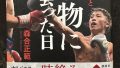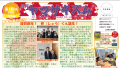消費税
消費税令和5年10月から消費税のインボイス制度が開始して2ヶ月ほど経過しました。「記帳業務が大変になった」とは職員の声です。お問合わせをいろいろと頂いていますが、インボイス制度の間違えやすいことを整理してみます。
取引先がインボイスを登録していなくても経過措置により、最初の3年間は80%の仕入税額控除、次の3年間は50%の仕入税額控除が認められています。6年間経過後は、消費税分が丸々損するということではありません。消費税に計上できなかった分は、経費として計上されます。実効税率を35%とすると、消費税額の35%は法人税等が少なくなります。例えば消費税額が10万円とすると、3.5万円は税金がお安くなります。
また、インボイスの登録をしていない取引先に対して、消費税分は支払いませんとは言えません。取引が減る、値下げ交渉の材料になることは考えられますが、課税事業者にならないからといって取引を打ち切ることは下請法違反となります。免税事業者の立場からは、事業を継続する場合、消費税を上乗せする価格表示は避けるべきといえます。
インボイス制度下の税務調査については、鈴木俊一財務大臣は「請求書等の保存書類についてなどの軽微な記載事項の不足を確認するための税務調査は実施しない」と国会答弁しています。星屋国税庁次長は「調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても他の書類等を確認するなど柔軟に対応していく」と答えています。様式にこだわってこれはインボイスになるのかという問合わせがありますが、登録番号、消費税額、消費税率などの要件を満たしていればインボイスとして認められます。そういうことまで調査官が調べていたら、税務調査の費用対効果に見合わないでしょう。大口で悪質な不正計算が想定されるものを対象にすると、鈴木大臣は述べています。
ただし、カードの利用明細はインボイスとはなりません。領収書・請求書が必要となります。交通系のカードなどは、チャージした月に全額交通費に計上するケースが見られますが、交通系ICカードリーダー(約5,000円)で利用明細が見れるようになっています。公共交通機関はその明細で良いとして、物販の買物などは領収書等が必要になり、それが無いものはそもそも経費として計上できません。これはインボイス制度というよりも、それ以前の問題です。