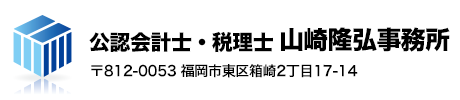元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
「給与所得者の特定支出控除」とは、給与所得者が勤務に伴って特定の支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。平成25年度以後の所得税から適用されています。
そもそも給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて異なります。平成28年度では、12百万円以上の給与収入で2,300千円控除されるのが上限です。平成29年度は10百万円の給与収入で2,200千円控除が上限となります。
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」は、平成28年度からは一律に「その年中の給与所得控除額×1/2」となります。給与所得控除額が上限の2,300千円の場合、1,150千円以上支出があれば、所得金額から控除できます。
「特定支出」とは、給与所得者が支出するもので、6つ定められています。通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費です。勤務必要経費は図書費、衣服費、交際費等となっており、65万円までとなっています。
なお、これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られ、それぞれ証明書の様式が定められています。給与の支払者から補填される部分がある場合には、支給部分は「特定支出」から除かれます。
この「特定支出控除」を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
1,800千円以下の給与収入であれば収入金額×40%が給与所得控除額となります。3,000千円の給与所得の場合は給与所得控除は1,200千円です。1,200千円の半分は600千円ですので、これを超える場合に適用となります。
給与所得控除は、サラリーマンの経費を認めているような制度です。それの半分といえども超えるのは、なかなか大変でしょう。